
小野小町のこの和歌は、
「古今和歌集」の「春歌下」に載っています。
(意味)
花の色は衰えて、色あせてしまった。
春の長雨が降り続き、
私は世を過ごすための空しい(むなしい)心づかいにかまけて、
花をみる余裕もなかった、そのあいだに。
「世にふるながめ」は、掛詞(かけことば)。
ふる→「経る」と「降る」
ながめ→「詠め(ながめ)」と「長雨」
つれづれなる春の夕暮れの、
長雨に降りこめられた憂愁が詠いあげられています。
新潮日本古典集成〈新装版〉 古今和歌集 (奥村恆哉 校注 /新潮社)によると、
小野小町のこの和歌は、
「古今和歌集」の「春歌下」に載っています。
奥村氏の解説によりますと、
もしこの歌が、
容姿の比喩と解するなら、
「雑歌」の部にあるべき内容であるし、
この説には根拠がないので、
言葉通りに理解するべきだ、
そうです。
「言葉通りに理解すべき」
『萬葉集』には、
萬葉集の特徴が、
『古今集』には、
古今集の特徴が
あるのだそうです。
万葉集には、
俗語や日常語を大切にして、
自分の気持ちを詠うような句が収められているのに対し、
古今集は、
表現が明晰であることが求めたらしいです。
「冗語(じょうご)を排し、
誤解を許さない、
それが『古今集』詞書の文体なのである」
歌の素材選択においても、
より明晰であろうとする志向は顕著で、
諸作品みな、
輪郭がはっきりした対象以外、
つかもうとしない。
「余情妖艶の体」は、
誰も詠まなかったのである。
たとえ詠んだとしても、
それが『古今集』二十巻のうちに採られることはなかった。(p398)
『古今集』が編まれた時代の律令制社会、秩序を、そのままに。
『古今集』は
紀貫之(きのつらゆき)の一貫した思想に支えられています。
紀貫之にとって価値があったのは、
人間と自然のあるべきありようだけ。
私的抒情の割り込む余地はない。
編纂方針にも、
歌の配列にも、
素材の取り方にも、
それがはっきりとあらわれているのですって。
歌の配列には、
『万葉集』と異なって、
四季の部は季節の推移に従い、
恋の部は恋愛の展開に従い、
順序正しく、
機械的ともいえるほど正確に配列されている。
この世のあり様、
人間のあり様を、
自然の鼓動、
人の呼吸に沿って写し取ろうとしている。
取り上げられた同一の素材、
桜なら桜、
月なら月は、
一群にまとめておかれ、
この配列基準は厳格だそうです。
作者名の記し方にも法則があり、
同一の巻で初めて出る時は氏名を記し、
再度出る時は名のみ。
そして、
当の作者が四位以上であれば、
氏名の下に「朝臣(あそん)」をつけて区別したそうです。
『古今集』の時代、「花」はまだ「桜」を指したわけではなかった
また、
「花」というとそれは桜のことを指していると私たちは思っていますけれど、
『古今集』では、まだ、その観念はなかったといいます。
歌の中に「桜」という語のない作では、
必ず詞書で「桜」と断っている。
だから、
全て歌の中に示されていないときは、
詞書でしっかり断ってあって、
例外はない。
これについて、
近世の古典研究に大きな足跡を残した
契沖(けいちゅう)は、
『古今余材抄』という注釈書で、
例を引いて分析を行っています。
「詞書にも桜と言わず、
歌にもただ花とのみよみたれば、
よろづの花をよめり」。
小野小町の詠った
「花の色は移りにけりないたずらに
わが身よにふるながめせしまに」には、
詞書がついていません。
なので、
「花」は、桜の花、というわけではなく、
どの花のことかは特にわからないっていうことですね。
『古今集』の編纂方針からすると、
隠された意味はないのではないかな?
一定の厳格なルールに基づいて、
歌が選ばれ、
配置されているのが、
『古今集』だとすると、
「春歌下」の部門にあるということは、
素直に季節を詠った歌、
と受け取るべきではないでしょうか。
この歌、どうも
齢を重ねることへの複雑な女心は、
関係なさそうなようです。。。


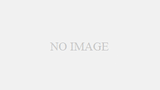
コメント